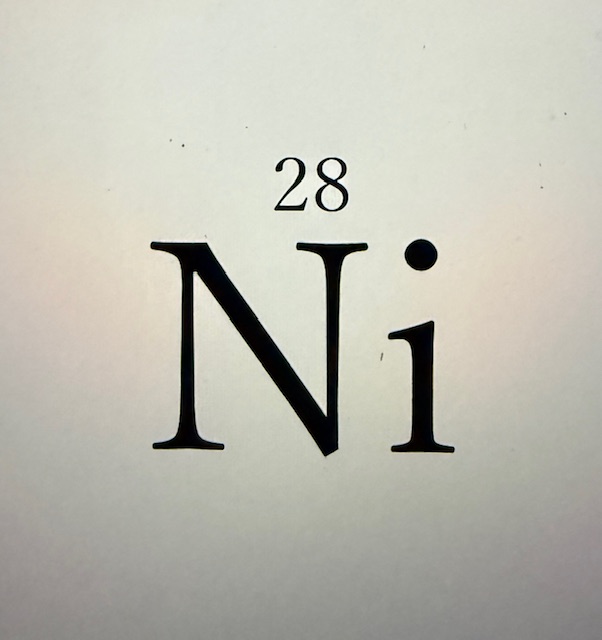パスタ用硬質小麦を
粗挽きした粉(セーモラ)に水を加えて練ったのがパスタだ。
最近は硬質小麦でないB級品・軟質小麦を一部加えて作るパスタもあるらしい。
軟質小麦が悪いわけではないので間違えないでほしいが、
『パスタ』とは硬質小麦と水で練ったもののことを言う。
軟質小麦は硬質小麦より安価、それのB級品とは
全ては『価格』『コスト』を抑える為。
#消費者を舐めてる
様々な人々が様々な倹約や工夫をする(これ皮肉です)
全ては、食べた時に本物かどうか、
味わいで違和感を感じたり、
食後感と、実際に咀嚼し身体に入ると体内での消化吸収に関係してくるから
みんな知っておかなければならないこと、と思いますよ。
日本人がパスタを本格的に食べ始めて50年ぐらいになるんでしょうか。
私の子供の頃はソフト麺だった。
調理済み(既に加熱された)ソフト麺がピチピチビニール袋に密封され、
フライパンで玉ねぎやピーマンを炒めてから
ソフト麺を袋から出し野菜に投入し炒め、
最後に付属のソースを加えて全体に炒めて出来上がり。
これがスパゲッティナポリタンの始まりだった気がする。
そのあとに、日清製粉のママースパゲッティーが登場する。
これはあくまで朝倉家での食卓でのスパゲッティの歴史(笑)ではあるが、
ソフト麺が先か、ママ―スパゲッティが先か、
定かではないが、
まあおおむね、日本のスパゲッティ事情はこんなもんだろう。
そんなことから、いまわたしは61歳なんで、
スパゲッティというものを食べて半世紀は経った、ということになる。
ケチャップ味のあのナポリタンは、
みんなが大好き、日本の味になったのではと思う。
わたしも無性に食べたくなる時がある。
和食が基本ではあるが、
ナポリタンやほかパスタが登場し、日常食になっていく。
#テレビの影響ね(CMや料理番組など)
食べるものとは、
留まることはなく、
次々に新しいものが登場し、それが定着し、そしてまた新しいものが・・・・と
繰り返すのではなく、変化していく、と言っていい。
食文化はとどまらない!
これは一人一人のチョイスでマーケットができ、広がっていく。
人が自由に世界中を移動でき、情報も豊富なので当然の流れ。
西洋の食文化はいかん、
和食中心に、とは、
ある程度腑に落ちるが、
人のチョイスをコントロールすることができないのが世の常。
だからこそ、
見極めないとね。
前回の新『アサクラパスタ物語』その⑪では
高温乾燥の危険性を具体的に製造ベースで書いた。
今回⑫では、
食べ物を(危険なパスタも)食べたらどうなるって話し。
健康を害することもなく、
毎日元気いっぱいであれば、
何を食べてもおいしく、たくさん食べても全く問題ない。
若い内は、全く問題ない人がほとんど。
だからお腹を満たせれば、味が良ければ
食品の裏側を見る機会もなく、興味もなく、
深堀りする機会はない。
わたしもそうでしたから(22歳まで)
何かのきっかけがない限り、気づくことは不可能に近い。
気づくのは自分も含め家族が健康を害した時がほとんど、
もしくは出産を機に生まれてくる子供のことを考えた時。
このどちらかではないだろうか。
パスタの話に戻すと、
パスタは、特に食べなくてもいいもんなので、
特に気にしてもらえない食品の一つだ。
パスタの何がいけないのか?
わたしは、マリオさんからいろいろと世界の現状を聞き、
現状のパスタの問題についてをこのシリーズの『その②』で書いたが、
問題の要点『熱による成分変質』について
詳しく書いてみる。
高温乾燥がなぜいけないか?
その⑪の『危険な高温乾燥パスタ』で書いた通り
パスタを袋に詰めて長期間保存させるために、
生麵を乾燥機に入れて乾燥させなければならない。
この時の乾燥温度が非常に重要で、
いったい何℃で乾燥すれば材料の成分が極力変質の方向に傾かないのか?
これは輸入する前にわたしが行き着いた課題だった。
この成分の変化の分岐点こそ、輸入したいパスタの目安だ、
そして70℃以上で乾燥させたものは
ゼラチン化とそれ以上の温度でガラス化という現象が起きることも前回その⑪で書いた通り。
さて、これら高温パスタが身体に入ったらどうなるのか?
これは茹でるところからイメージしてもらいたい。
ゼラチン化した、
またガラス化まで到達したパスタをお湯に入れてゆでる。
これら高温で乾燥したパスタは、
表面が溶けて再度固まりラップをしたようになっており、
(これをわたしはメルティパスタと命名)
メルティパスタは、
茹でた時に麺にお湯が浸透するのに時間がかかる。
#カッチカチになってますからね。なんてったってガラス化だからガラスのように硬くなってる
だから茹で時間も長い。
カチカチになっておりしかも表面がラップしたようになっているから
中の成分も外に出ない
だから茹で湯も濁らない。
アルデンテにゆで上がっても、アルデンテをずっと保っていくれる。
#ここがね、違うんですよ劇的に。一般品とアサクラパスタ。アサクラパスタはアルデンテ、保てません
(メルティ麺を)口に入れ、もぐもぐ噛む。
『噛む』とは、咀嚼とも言い、
噛むことにより口の中で食べ物を細かくし、
次の工程(食道を通し胃へ)への負担を軽くするために行う。
この時に、
よく噛むと、唾液が沢山出ることになり、
唾液には消化酵素(アミラーゼ)が含まれているので
この酵素によって食べ物の消化を促す。
メルティパスタは
噛んでもアミラーゼがパスタ成分まで到達しないという。
硬すぎるから💦
#変質してしまっている別な物質になったよう
また蕎麦を食べ慣れた日本人は、
箸でスパゲッティを食べる(得に男性)人は、パスタをかまずに飲み込む。(きゃーーーー)
#スパゲッティはフォークでくるくるして食べて下さいそうすると噛めるから
#メルティパスタをかまないで飲み込むと・・・・
ここまででも、メルティパスタがかなり危ないのは想像できるでしょう!
メルティパスタは、
①消化に良い加熱地点まで到達しない(粉成分の芯までお湯(水分)が届きにくい)
②茹らない状態で食べることになるので消化に時間を要する
③噛んでも唾液として分泌される消化酵素がパスタの成分に到達できない
④噛まないで飲み込むと口内で出来なかった咀嚼の分を胃で負担しなければならない→胃液過剰分泌
※胃液が過剰分泌すると胃が炎症を起こす原因になる
⑤胃から次は十二指腸(胆汁や膵液が分泌され消化・吸収しやすくし)→小腸まで届く
そのすべての分泌物が過剰になる、時間も要する
⑥小腸に到達して体内に吸収されるが、ここで吸収できなかった残存物は大腸まで届く
口から物が入ると、休むことなく小腸や大腸で吸収されるまで
分泌物やら臓器がフル回転し頑張ってくれる。
年を取ると消化しにくいものを食べると、
胃辺りからの消化されているのがなんとなくわかるようになってくる。
食後感とはよく言うが、それだ。
ずーーっと胃の中で留まっているのがわかる時がある。
そして時間になってもお腹が空かないってのもその一つ。
以上、
食べ物の消化について大体イメージできるたのではないかと思う。
イタリア人は基本、毎日パスタを食べている人が多い。
わたしが住んでいた25年前の南イタリアは、そうだった。
毎日、昼に乾麺をお母さんが茹でる。
ソースは毎日違う。
またパスタの型も毎日変わる。
ペンネやフジッリやリガトーニや、
長いスパゲッティだったり、毎日変えてくれるので、
全く飽きなかった。
たぶん、この人たちは、
わたしが来る前から、、そして去った後も、
ずっとずっと、
乾麺パスタを食べ続けているのだろう。
それがメルティパスタだったらどうなるか?
マリオさんの話に戻すと、
ただでさえ、
ビスケットや朝食べるクロワッサンや、焼き菓子、
そして食事中のパン、
夜はピッツア、などなど。
小麦製品に囲まれ、小麦加工品を食べない日はないイタリアの人々。
戦後食糧難が解消され、
食べ物も豊富になり、
小麦系アレルギーが出始めたのが、
今から40年前ぐらいからそうだ。
#戦後80年の現在
マリオさんの製麺所に、
アレルギー対応食品を供給する食品業者が
訪れるようになり、
マリオさんに安全な粉、また小麦でない原材料を持ち込み、
パスタを製造してもらい、イタリアはもちろん
世界中で販売するようになる。
その製造をしながら、
さまざまな症状のアレルギーの現状を知ったマリオさん。
イタリア(だけとは言わず世界的に)
まず金属アレルギーとグルテンアレルギーがほぼ同時に
増え始めたそうだ。
金属は金属でも鉱物の『ニッケル』アレルギーだそうで、
小麦や麦には微量成分としてニッケルが含有する。
グルテンフリーとありますが、
グルテンフリーとは、
『グルテンを含む食材を使用しない』という意味です。
または『グルテン無し』
グルテンとは、
小麦にだけ含まれるたんぱく質を構築する物質の名称で
小麦がサラサラの状態の時にグルテンは生じていません。
水を加えて捏ねると目に見える現象があります。
粘り気や、弾力。
これがグルテン。
グルアジン(粘り)とグルテニン(弾力)の2種が一体になり
『グルテン』と呼びます。
さてここからが
世界中の人が勘違いしていること、、
とわたしは思っています。
グルテンを食べ過ぎたから、グルテンアレルギーになった?
セリアック病やグルテン不耐症、小麦不耐症、リーキーガット症状など、
これらの原因はグルテン、と言われている。
はて、そうだろうか。
グルテンアレルギーとほぼ同時期に起こったもう一つのアレルギー
金属アレルギーは、
ミネラルであるニッケル(Ni)に反応してと書いたが、
さて、ニッケルを食べ過ぎたからだろうか?
ニッケルによる金属アレルギーを発症した人は、
パスタそしてトマトにも反応するようになり、
トマトには微量だが、ニッケルが含まれている。
トマトが悪なのであろうか?
グルテンは、
小麦にだけ含まれている唯一の成分であると書いた。
グルテンを含む小麦を食べたからだろうか?
ある意味そうなのであるが、
ニッケルに反応する金属アレルギーも
グルテンに反応するグルテンアレルギーも、
その食材自体に反応したからではない。
材料のあやしい由来や人の消化に耐えられないように加工された食品を摂取してきたからに他ならない。
リーキーガットは、小麦だけでなく食習慣や食品添加物の問題も含むしね。
つまり、
お店に売っているものであれば、
どんなものでも食べてもOKと疑いなく食べることに問題がある。
小麦に含まれるグルテンは、
水と捏ねて酵母を加えると発酵し、
炭酸ガスが発生するが
グリアジンとグルテニンが生じるお陰で伸びてどんな形状にも変えてパンを作ることができる、
グルテンがあるおかげで、
おいしいふっくらとしたケーキを作ることができる。
グルテンがあるおかげで、
歯ごたえのある、うどんやパスタができる。
小麦で作る食品は『グルテン』という小麦にしかない唯一の特徴、
グルテンがあるおかげでさまざまな形状を変えた印象もまったく変わる
食品が出来上がる。
グルテンってすごいんです!
小麦の歴史にまで話を派生すると、
1万年前から古代の人は麦類を食べている、一度として廃れることなくだ。
この小麦系アレルギーは近年に始まっている。
それは食品が、本来の食品からかけ離れ始めた時からだ。
コストや効率を軸に製造される食品を我々現代人がむさぼり食らうようになってからだ。
さきほどのニッケルアレルギー。
これになってしまうと、
ニッケルを含む、トマト以外の食材にも反応する可能性がある。
特定の食材がわたしダメってのありませんか?
それは、その食材を食べ過ぎたからでなく、
それを引き起こす別な食品を食べ続けたから、と考えられる。
グルテンや金属アレルギーはあくまで『結果論』なのです。
腸を含め内蔵に負担のないような食品を選ばなければならない、ってのは
これでお判りいただけたのではと思う。
メルティパスタだけでなく、
あらゆる食材が、
そして過剰に飲んだり食べたり、
が胃や腸やあらゆる器官に負担をかける。
症状として現れる人とそうでない人がいるが、
その人が生まれてからこれまでの食べてきたものと生活習慣、
そしてDNAまでも関係していると言われている。
身体はある意味、デジタル!
原因と結果が連携しており、
原因不明ってありますが、
原因不明は、われわれ人間がまだ解明できていないってことですから。
それと過去の食歴や家族の生活習慣ぜーーーんぶが総合して症状が現れる。
だったら
その症状が出ると思われるような食品を排除することが先決。
また睡眠や(食べ方・噛み方)食習慣、生活習慣を変えることも重要。
安易にグルテンフリーにするっていうのとは違う。
オリーブオイルだって同じ、
どうでもいい粗悪品、
一般の人は想像もできないような粗悪なオリーブオイルが製造されている。
そういうものを取り続けたら、
メルティパスタと同じだ。
粗悪品ほど身体に負担がかかる。
『〇〇が悪』や『〇〇が病気の原因』なんて
食品をつるし上げ『悪』という人がいますが、
それも違うと思う。
症状は食習慣と生活習慣、そして本来のものではない粗悪品の摂取による、
身体への負担(あと家族の素養や持って生まれたDNA)
わたしたちは過去の履歴を全部しょって
今生きている。
症状はそのれらを含めた膨大な体の履歴の現れだとわたしは思う。
次号に続く